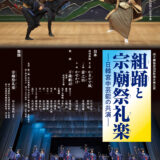プログラム
斉唱「そんばれ節」「黒島節」
舞踊「柳」
独唱「下出し述懐節」
独唱「赤田風節」
– 休憩 –
◼︎ 斉唱「そんばれ節」「黒島節」
そんばれ節
一、今年から始まる そんばれの踊り 二才ばかいすだして 踊らし舞らし 前結びもかたけさまも つやうつやうらさ
今年から始まる そんばれの踊り 若者を装わせ 踊らせ舞らせて 前結びも かたかしらも 清らかで美しい
二、鶴と亀との齢や 千年万年 我ぬも年比べて 幾世までも 子孫さも もていさかえ
鶴と亀の年齢は 千年万年 私も年を比べて いつまでも 子孫の繁栄を願いたい
黒島節
一、千歳へる松の 緑葉の下に 亀が歌すれば 鶴や舞方
千年を経た松の 若芽の下で 亀が歌をすれば 鶴が舞っている
- そんばれ / 西表島租納の小集落名
- 二才 / 若者・青年
- かいすだして / 装って、化粧して
- 前結び / 王朝時代の男性の琉装で締める幅の広い大帯
- かたけさま / かたかしら。王朝時代の成人男性の髪型
- つやう / 実に、誠に
- つやうら / 清らかだ
- 齢 / 年齢
- 我ぬも / 私も~
- 幾世までも / いつまでも
- もたへさかえ / 繁栄、栄える
- 緑葉 / (若い)芽の葉
若者の清廉な舞いに長い人生の幸先を願い、子孫繁栄、健康長寿を祈願する内容が歌われます。琉球舞踊「松竹梅鶴亀」でも演奏され、歌詞には「鶴」「亀」「松」などのおめでたい言葉が並びます。
演奏動画はこちらから → YouTube「そんばれ節」「黒島節」
◼︎ 舞踊「柳」
中城はんた前節
一、飛び立ちゆる蝶 まずよ待て連れら 花のもと我身や 知らぬあもの
飛び立っていく蝶 まず待って一緒に連れよう 花のところを私は 知らないので
柳節
一、柳は緑 花は紅 人はただ情け 梅は匂い
柳は緑 花は紅 人はただ情け 梅は匂い
- 飛び立ちゅる / 飛び立っていく
- 蝶 / 花の縁語で、誘いに来た友を蝶に擬した表現
- つれら / 連れよう、一緒に行こう
- あもの / 〜であるから(順接の接続詞)
琉球王朝時代に育まれた古典舞踊の「女踊」にあたる作品で、自然の摂理と人間の姿を描いた作品です。一曲目は、花籠(はなかご)を肩にかついだまま所作が展開され、舞台中央奥に歩み花籠を置きます。二曲目は、「柳は緑」「花は紅」「人はただ情け」「梅は匂い」の内容に沿って所作が構成され、小道具を持ち替えたり、手踊りで歌詞のテーマを表現します。「こねり手」「抱き手」、片足立ちで調子をとる動きなど、琉球舞踊における所作が随所に散りばめられています。
演奏動画はこちらから → YouTube「中城はんた前節」
コラムはこちらから → 琉球舞踊「柳」によせて⦅髙井賢太郎⦆
◼︎ 独唱「下出し述懐節」
朝夕さもお側 拝み馴れ染めの 里や旅せめて いきやす待ちゆが
- 朝夕さも / 朝に夕に、いつも
- 里 / あなた(女性からみた男性)
- 旅せめて / 旅に出て、旅立って
- いきやす待ちゆが / どうお待ちすればよいのか
「述懐節」と節名がつく古典音楽は複数あり、〈本調子(ほんちょうし)〉〈二揚(にあぎ)〉〈下出し(さぎんじゃし)〉など、調弦や歌い方の違いによって、それぞれが独立した楽曲となっています。感情の高まりを高音域の歌声で表現する「二揚」に対し、「下出し」は低音部から歌い出され、しみじみとした曲調が聴きどころ。歌詞は、愛おしい男性の旅出を見届けた女性の切ない心情が描かれます。琉球舞踊の名作「花風(はなふう)」でも演奏され、人気を誇る楽曲です。
コラムはこちらから → 「下出し述懐節」によせて⦅町田倫士⦆
◼︎ 独唱「赤田風節」
赤田門や つまるとも 恋し見物門や つまてくれるな
- 赤田門 / 首里城の外郭に位置する「継世門」の古称
- つまる / 閉まる
- 見物門 / 首里城の内郭に位置する「淑順門」の古称
- くれるな / ~してくれるな
和歌と琉歌の詩形を組み合わせた「仲風(なかふう)形式」で歌われる楽曲です。歌詞に出てくる「見物門」は、王室に仕える女官たちが住む男子禁制の奥御殿・御内原(うーちばる)へ続く門であることから、城内の厳しい規律のもとでの恋愛や密会への憧れを詠んだものと考えられています。中低音域かつゆったりとしたテンポが特徴で、独唱曲としても好まれています。
コラムはこちらから → 「赤田風節」によせて⦅棚原健太⦆
◼︎ 舞踊 「江佐節」
渡りざう ※歌なし、器楽演奏のみ
瀧落菅攪 ※同上
江佐節
一、沈や伽羅とぼす 御座敷に出ぢて
沈や伽羅の御香を焚いた 御座敷に出ると
二、踊る我が袖の 匂いのしほらさ
踊る我が袖の 匂いが可憐である
三、踊る我が袖の 匂いのしほらさ
踊る我が袖の 匂いが可憐である
- 沈や伽羅 / ともに香木の名前。沈香と伽羅の香
- とぼす / ともす。つける
- 出ぢて / 出て。出でて
- しほらさ / 可憐である
昭和初期に舞踊家・玉城盛義(1889~1971)が振り付けたとされ、以来、多くの舞踊家や流派によって受け継がれている作品です。白ハチマキや脚絆を身につけた男性の装束で、華やかな楽曲に合わせて躍動感あふれる所作が展開されます。
演奏動画はこちらから → YouTube「江佐節」
◼︎ 舞踊「谷茶前」
伊計離節
一、勝連の島や 通い欲さあすが
勝連の島に 通いたいのだけれども
二、和仁間門の潮の 蹴やいあぐで
和仁間門の潮は(波が激しいので)行きあぐねているのだ
谷茶前節
一、谷茶前の浜に スルル小が寄てぃてぃんどー スルル小が寄ててぃてぃんどー
谷茶村の前の浜にキビナゴが寄り集まっているよ
二、スルル小やあらん ミジュン小どやんてぃんどー ミジュン小どやんてぃんどー
キビナゴではないよ 大和いわしなんだよ
三、二才達やうり取いが あん小や かめてうり売いが あん小や かめてうり売いが
青年たちは魚を取って 若い女性たちは 魚を頭上に乗せてそれを売りに
四、うり売ての後の あん小が匂いのしほらさ あん小が匂いのしほらさ
魚を売って帰ってきた 若い女性たちの 匂いが香ばしい
- 勝連の島 / 沖縄本島中部にある勝連半島にある集落
- 通い欲さあすが / 通いたいのではあるが
- 和仁屋間 / 地名。沖縄本島中部北中城村にある
- 蹴やいあぐで / 蹴り歩くのが難儀である
- 谷茶 / 地名。沖縄本島北部恩納村にある
- スルル小 / きびなご
- 寄てぃてぃんどー / 寄ってきだぞ
- あらん / ~ではない
- ミジュン / 奄美島以南に生息するイワシ
- 二才達 / 青年たち
- あん小 / 若い女性たち
- かめて / 頭上に物をのせる
- しほらさ / 香ばしい、快い、可燐である
谷茶とは沖縄本島北部西海岸の恩納村の地名です。かつては漁村として栄えていました。谷茶の浜辺で男達が魚を獲り、村の娘たちがその魚を町に売りに行くという漁村の情景を歌っています。雑踊「谷茶前」は、明治20年代に振り付けられ、男は櫂(かい)を、女は籠(かご)を持って踊ります。
演奏動画はこちらから → YouTube「谷茶前」
◼︎ 舞踊 「浜千鳥」
一、旅や浜宿り 草ぬ葉ぬ枕 寝ても忘ららん 我親ぬ我親の御側
*囃子 チヂュヤーヤ ハマヲゥティ チュイチュイナ
旅は浜辺を宿にし 草の葉を枕にする 寝ても忘れられないのは 我が親のお側
二、旅宿ぬ寝覚め 枕すばだてぃてぃ 覚出すさ昔 夜半ぬ辛さ *囃子
旅宿で目覚め 枕をそばだてると 思い出すよ昔 そんな夜半が辛い
三、渡海や隔じゃみてぃん 照る月やふぃとぅち あまん眺みゆら 今日ぬ空や *囃子
海を隔てていても 照る月はひとつ あの方も眺めているだろう 今宵の空を
四、柴木植いてぃ置かば しばしばとぅいもり 真竹植いてぃ置かば またもいもり いもり忍ば *囃子
柴木を植えておくので しばしばとおいでください 真竹を植えておくので またもおいでください
- すばだてぃてぃ / 枕などから頭を持ち上げて聞き耳をたてる
- 夜半 / 夜中
- 渡海や隔じゃみてぃん / 遠く海を隔てても
- あまん眺みゆら / あの人も眺めているであろう
沖縄の人々は遠く離れた地からふるさとを想う心情を、浜で遊ぶ千鳥に託してきました。明治期には「浜千鳥節」に踊りが付けられ、「チジュヤー」の愛称で、歌・踊り共に現在でも多くの人に親しまれています。「うちなーカンプー」と呼ばれる髪型に、紫のサージ(布)を頭に巻き、紺地の琉球絣を着用します。また、帯を用いない「ウシンチー」という沖縄独特の着付けも見どころです。
演奏動画はこちらから → YouTube「浜千鳥」
琉球芸能活動中 – リュウカツチュウ –

芸術文化活動が制限された2020年10月感染症流行(コロナ)の真っ只中、活動を開始。沖縄にいなくても、沖縄に・伝統に触れる場所をつくりたいという想いから
「 海だけじゃない、沖縄の魅力
首里城だけじゃない、沖縄の宝もの 」
をコンセプトに沖縄や伝統をYouTubeや舞台にて発信。それぞれ三線、琉球舞踊、琉球箏の舞台活動に取り組んでいます。
▶︎これまでの活動
ー 国立劇場おきなわ連携動画の企画、撮影、編集等
ー 三陸AIR・アーティストインレジデンス 「琉球と三陸の芸能交流」
ー なら国際映画祭 フランス・パリ/コルシカ島 琉球舞踊及び古典音楽 公演
ー 沖縄タイムス日曜子ども新聞「ワラビー」連載(第3週8面)
その他、県内外による琉球芸能公演(琉球舞踊、組踊、沖縄芝居等)、WS等に出演
◼︎ PROFILE

髙井 賢太郎 -TAKAI KENTARO-
琉球舞踊/組踊 立方
玉城流敏風利美の会。仲間若菜、安次嶺利美に師事。沖縄県立芸術大学 大学院 音楽芸術研究科 舞台芸術専修 琉球舞踊組踊専修 修了。琉球新報 琉球古典芸能コンクール 琉球舞踊部門 最高賞 受賞。国立劇場おきなわ 第五期 組踊研修修了者。国立劇場おきなわ主催公演はじめ県内外での舞台出演やワークショップや組踊の普及活動に取り組む

棚原 健太 -TANAHARA KENTA-
琉球古典音楽 歌三線
琉球古典音楽野村流保存会。比嘉康春に師事。沖縄県立芸術大学 大学院 音楽芸術研究科 舞台芸術専攻 琉球古典音楽専修 修了。沖縄タイムス 伝統芸能選考会 三線の部 最高賞 受賞。後、グランプリ 受賞。国立劇場おきなわ 第四期 組踊研修修了者(一財)地域創造 公共ホール邦楽活性化事業 登録演奏家(令和4・5年度)。国立劇場おきなわ主催公演はじめ県内外での舞台出演やワークショップや組踊の普及活動に取り組む

町田 倫士 -MACHIDA NORITO-
琉球箏曲
琉球箏曲興陽会。山内照子に師事。沖縄県立芸術大学 大学院 音楽芸術研究科 舞台芸術専攻 琉球古典音楽専修 修了。琉球新報 琉球古典芸能コンクール 箏曲部門 最高賞 受賞。国立劇場おきなわ第五期組踊研修修了者。国立劇場おきなわ主催公演はじめ県内外での舞台出演やワークショップや組踊の普及活動に取り組む
主催:琉球芸能活動中 – リュウカツチュウ –
共催:琉球コンパス合同会社
特別協賛:株式会社 BOX4628